2024.02.25 吉祥寺国際アニメーション映画祭
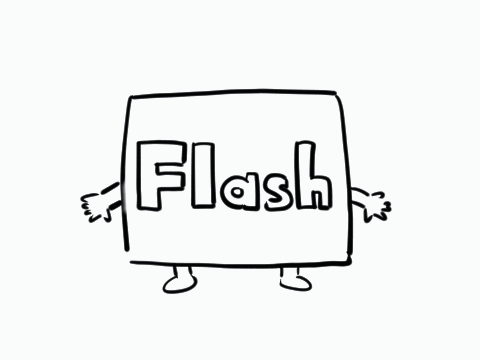
吉祥寺国際アニメーション映画祭の3日目、コンペの本選と表彰式を見に行ってきました。
もう長年気になっていた映画祭なのですが、実は近い日付で行われる「三鷹の森アニメフェスタ インディーズアニメフェスタ」とずっと混同していました。
ずっと混同しながらも、例年ものすごく忙しい時期なので、数年に一回三鷹の森の方で当選した上映会に行くくらいしか参加したことがありませんでした。
ちょっと整理しておきますと
吉祥寺国際アニメーション映画祭
・武蔵野市が主催
・場所:武蔵野公会堂
・今年は3日間(例年のことは存じ上げず)
・3日目に最近の作品のコンペあり 入場無料でいきなり行っても入れる
三鷹の森アニメフェスタ
・三鷹市主催(?)
・場所:三鷹市芸術文化センター
・例年2日間
・1日目午前短編アニメ(新旧含む)、午後長編アニメ(近年のもの) 入場無料だけど抽選式
・2日目インディーズアニメフェスタ 最近の作品のコンペ 入場無料でいきなり行っても入れる
共通点
・ジブリ美術館が協賛してる
三鷹市と武蔵野市、隣接してますし、どっちもジブリ美術館が絡んでるし、ノミネート作品もかぶってたりするし、この時期とにかく忙しいしで、いつか行きたいと思いつつ、今年初めて別々のイベントだったんだな、とついに知った次第です。
さて、今回行ってきたのは武蔵野市の方です!
冷静に考えてみると、コンペの上映って広島かノルシュテイン大賞しか見たことがなかったかもしれません。その2つと比べるとかなり小規模なコンペでした。だからこそ、おもしろかったです。
ノミネートされた14作品それぞれのアニメーションの方向性があって、存在意義がちゃんとあるということを教えてくれたとてもいいコンペでした。
私が短編アニメーションの世界に興味を持ち始めた20年ほど前、まだアニメーションってこういうものっていうフォーマットがあまり決まっていなかったような気がします。ごく一部のものすごくコツコツ作業できて、環境に恵まれたり努力してそれを手に入れた人が、ストーリーを作って映像化していたり、または自分の内面や記憶を効果音大き目に演出して描いたり、とりあえず何かをどうにかして動かしてみたり…とにかくセルアニメとは違う手法で何かを動かして何かを表現する、というものでした。
それがだんだんと洗練されていって、最近ではこれが正解だよね、みたいなフォーマットができてきた気がします。それを作ったのが藝大大学院の教育なのではないかな、と私は勝手に思っています。
確かにすごい。今回グランプリを取った「月見ごこち」も藝大大学院の方の作品でしたが素晴らしかったです。上映終わった瞬間に、これがグランプリなんだろうな、と確信しました。
一方で、受賞発表後の審査員トークで片渕さんが言っていた「何を描くか」「どう描くか」がだいぶ画一化してきたな、というのもひとつの感想でした。
(あ、これでは誤解を生みますね。画一化してきたな、というのは私個人の感想で、片渕さんは問いだけを提示されていました。そしてだからこそ次のアニメーションの新しい突出した表現、何かが出てくるのを期待して待ってる、と)
最近私は自分の作品の構想を練っていたのですが、どうにも頭の中であ、こうすればいわゆる短編アニメっぽくない?みたいなイメージがすぐに湧いてきてしまうのです。そう、アニメーションの正解フォーマットってこういうものだよね?みたいなものがひとつ自分の中で完成してしまっていたのです(作品として作ったことはないくせに!)
それに対して、今回の吉祥寺国際アニメーション映画祭は、荒削りだけど何かアニメーションの別の側面を見つけ出そうとしている作品が残っているように感じました。それは新しいものでもあれば、これが正解とされてきた中でそっちは違うんじゃない?とされてきちゃったけど、やっぱりいいよねアニメーションのそういうとこ、と思わせてくれる古き良きアニメーションの世界観だったりと、いろいろなものがありました。
新しいものでいえば、トークの中でも度々あがっていた「長期介護」という作品です。
実は私はこの作品を見ながらテーマもナレーション内容もすごくいい、でも絵柄が普通のセルアニメっぽいのが惜しいなぁと思っていました。が、審査員トークを聞き終えたあとに思ったのは、この作品がもし、いわゆるアートアニメーションの体裁を整えていたら、枠の中に収まって今回の仕上がりほど多くの人の胸に突き刺さらなかったかも、という全く反対の感想でした。
「長期介護」はおそらくご本人の実体験が元になっている作品で、10年間、祖父の介護をしてきた青年が、祖父が亡くなり、就職する段階になって自分が過ごしてきた10年間を振り返る内容です。いわゆる自己回顧ものなのですが、この作品が他と違うのは、ものすごく私的なことを描いているようで、誰の心にも共通する何かを描いているという部分だったと思います。例えていうなら、太宰治にとても近いんです。または東電OL殺人事件か。みんながみんな、彼になる可能性もある、あった中で、生きている。たまたま彼にならなかっただけだったり、まだなっていないだけである、そんなふうに思わせてくるものがあるのです。
もうひとつ、同じような自己回顧の作品であった「A Shape pf the Elephant」「月見ごこち」と徹底的に違うのは、彼はこれを描かなくてはいけなかった、という点だと思います。おそらく、「A Shape pf the Elephant」「月見ごこち」は先にアニメーションを作りたいという気持ちがあって、そのための題材を自己の中に探していった結果生まれたものだと思います。しかし「長期介護」については、作者がこれを乗り越えなければ次にはいけない、ではどうやって表すか?アニメーションにしよう、というところからスタートしたのではないでしょうか。
私はご覧の通り気ままに文章を書くことがあるのですが、書くことで整理ができることってあると思うんです。まあ自分の中にあったもやもやを形として掴んで手放す、とまではいかないんですが。ひょっとしたら「長期介護」の作者も作品の印象ほどはスッキリしてないかもしれないけど、確かに何かワンステップあがるためのアウトプット、それをアニメーションでやったのが、この作品だったと思います。これぞ、アニメーションの新しい形なのではないかと思います。筆をとるようにアニメーションを作る時代が、ついにやってきたということなのではないでしょうか。
絵柄についてさらに踏み込んで考察してみましょう。
おりよくAdoさんの新しいMVが公開されました。私も気になっているiPadのアプリ、Procreate Dreamsで描かれたとか。うーん、私は正直もっと動かしてもいいんじゃない?整えてもいいんじゃない?せっかくそのアプリ使うならもっと絵画みたいな絵柄にしてもいいじゃない?なんて思ってしまいましたが、ひょっとしたら整えて動かしていく中で失われてしまうものがあったのかも、最近の若者たちは知ってか知らずかそのことに気づいていて、わざと荒削りのままにしているのかな…なんて視点も今回コンペに鑑賞していて思いました。
というのも、審査委員長の竹熊さんがトーク終盤でおっしゃってたんです。このコンペを始めたのは、FLASHアニメが世に出てきたことがきっかけだった、と。
F・L・A・S・H・アニメ〜!!
なんて懐かしい響きでしょう。
(※Flashとはソフトの名前です。現在ではAnimateという名前に変わっています)
私もAnimate使いですからね、FLASHといえば、ある意味距離をおきたい親戚みたいなものであり、あくまでも自分のルーツのひとつでもあるやっぱり親戚みたいなものです。もう今の時代だと見れないかと思いきや、HTML5で書き出し直せば見れるんですよ…と、脱線しすぎるのでその話は置いておきましょう。ついでにもう一個置いていくつもりで書きますが、FLASHアニメが私にとって微妙な理由は、私自身は同じソフトを使ってても可能な限り動かしたいと思っている人なのですが、ソフトの名前だけ聞いて、ああFLASHね、あれ動かないでしょ?安くていいでしょ?というお仕事が結構多かったからです。はい、この話は置いておいて…
FLASHアニメといえば20年前というか、もはやそれよりさらに数年前、大学1年生(追記:記憶違いで本当は2年生)だった私が近所に住む先輩の家に行って、初めて「CATMAN」という作品を見せてもらった時に受けた衝撃は忘れ難いものでした。テレビアニメやジブリにはない、最小限に止めた動きの中にドラマがある!見える!見えるぞ!!と感動したものです。
ちなみになぜ近所の先輩の家に行ったかというと、私の家にはインターネットがなかったからです。3年生になってやっとネットをひいたんです。尚、その先輩は当時携帯電話を持ってませんでした。二十数年前ってそんな時代。そういう時代、もう遠い時代、若かった時代。
そう、あの頃のフレッシュな感覚、まさに若かったからこそ響いたあの感覚を思い出しました。
そうか、あの感覚がそのまま今はメジャーにのって商業にのっている時代なんですね、と突然何かが開眼した気がしました。そしてどこかでそこに若気の至りを感じつつ、眩しさ羨望を感じる自分がいることに気がつきました。
今までは、もう20年かけて、とにかくグランプリを取ったような作品こそが素晴らしいという感覚を自分の中に築き上げていってたんです。その感覚は残ったまま、同時に自分が知らず知らずのうちに閉じていっていた扉の向こうにも、新しい道が続いていたのかもしれない、という感覚が開きました。
そんな気づきを経た末に、作品の構想を練ろうとするたびに、こうすれば正解でしょ?と言ってくる心の声と、戦ってみるのもいいかもしれない、そんなふうに思い始めています。昨日の今日で、ですが。昨日の今日なのでまだ結論はでていません。正解でしょ?の声にくるまるのもいいかもしれない、でも、戦ってみたいな、そんな気持ちの方がちょっと強いかも。シーソーが動き始めました。
ねぇ、どこかで見たことある何かじゃないもの作れたら、失敗したっていいんじゃない?
----------
追記:当初「CATMAN」について2001年1月〜3月頃の公開という前提で書いてましたが、ウィキペディアによると2002年との表記がありました。
ニコニコ大百科によると”2001年、shockwave.comにおいて公開開始”となっています。
当時の先輩と作者の青池良輔さんに確認したところ、先輩からは、はっきり覚えてないが卒論を書いてた気もするから2001年かもしれない、とのこと。
青池さんからは、しっかりとは記録がないものの2002年1月公開というweb記事が残されているので、これが正しいのではないかとお返事をいただきました。
ということで、当初2001年を想定して書いていましたが、「CATMAN」の公開年は2002年1月と変更いたしました。
お忙しい中丁寧にご対応くださった青池さん、先輩、ありがとうございました。
|
|
2024.01.31 2024年1月終わり

こんな自己啓発的なこと以外にもいろいろ面白いことはあったのですが、それはちょっと置いておいて…1ヶ月の振り返りをどうぞ。
1月気付きその(1)
アレグラをやめたら本当に元気になった、気がする
2023年の振り返りにも書きましたが、2023年の花粉症シーズン以降ずっと半量の抗アレルギー薬アレグラを飲み続けていました。それを漢方薬の小青竜湯に変えてみたらなんだかすっかり元気になりました。ひょっとして2023年の私はずっと抑鬱状態だったのでしょうか。まあ今はもう元気なのでいいとしましょう。
ちなみにアレグラを飲むようになった原因の突然の鼻水についてはまだ原因究明中です。今ちょっと怪しいなと思ってるのがアルコールです。
1月気付きその(2)
マンガン電池はすごい
昨年家庭内引越しをして各自の部屋を設けて以降、100円ショップで買った小さな時計を家中に置いていました。これがマンガン電池指定の時計。そういえばアルカリ電池とマンガン電池の違いって何なんだろう?調べてみたら、「マンガン電池はしばらく休ませると復活する」という記述を見つけました。
そんなことあるの?と思いつつ調べたことも忘れていた頃に、家中の時計が止まり始めました。いやでも100円ショップのものだしな、なんか電力消費の個体差とかありそうだし、こっちの電池をこっちの時計に入れ替えたら動くんじゃない?と思って入れ替えたら本当に動きました。そういえば止まってから3日ほど放置してから入れ替えたものだけど…と今度は別の時計が止まった時に放置してから針の位置を戻してみたら、その後はなんと時刻が遅れることなく動き始めました。
ここで遠い記憶が蘇ってきました。昔、実家で電池が外された時計があり、母にこれは?と聞いたら「あぁいいのいいの、はいこれでOK」と元の時計に入れていたことを。
アルカリ電池かエネループなどの充電池がすっかり身近な日々に慣れきっていた私にとってこれはちょっとした衝撃でした。消耗される一方なのが当たり前の電力が、再充電ではなく、ただ休ませるだけで復活するなんて。
私は今まで人間の一生も寿命に向かって消費していく一方だと思ってたんです。でも、マンガン電池みたいにちょっと休むことで、その人の人生が思わぬ復活を遂げることがある、残りの人生をグイッと別の方向に向かせることもできたらいいな、と、この小さな電池から勝手に学び取り、感動した出来事でした。
1月気付きその(3)
頑張れば9.5時間までいける
2023年の振り返りの中で、1日あたり集中できる時間は6時間、と書きましたが、あれ本当は4時間くらいなんですよね…。なんで嘘を書いたかというと、毎日9時間も保育園に預けているのに4時間と書くのは申し訳ない気がしたので…。ほんと9時間も預けてるのになんで?といった感じですよね。
<理由1>
まず9時間預けられていませんでした。
次男の出発時間がどんどん遅れて実質8時間弱しか預けられてないことがしょっちゅうでした。
<理由2>
朝の家事の効率が悪く午前中がつぶれがち。
<理由3>
歩かないと腰痛になるので歩きに行く。着替えて昼食食べて、歩いて帰ってついでにポストのチラシをゴミ分別するなどしてるとあっというまに1時間半くらい過ぎる。
問題点を洗い出せたところで対策を練りました。
<対策1>
次男を送ってく当番は夫なので夫にハッパをかけました。最近また緩み気味なのでハッパかけ直します。
そして次男を効率よく起こすために一度夫に泣かせてもらい、かーちゃんがそこに救出に向かうという流れを毎朝作ることに。毎朝泣かされる次男はかわいそうですが、そこまでとーちゃん相手に嫌がらなくてもいいだろうに、とも思います。
<対策2>
夫が在宅の日も私の家事には手を出させない。
夫は週2日在宅勤務の日がありまして、その日は家事を何かと手伝ってくれてたんですが、そうすると毎日やることが変わってしまうので何をどう効率化したらいいのかがずっと見えてこず困ってました。なので思い切ってもう手伝わないでほしいと伝え、徹底的に自分の行動を見直しました。そしたら11時近くまでかかることもあった家事が今は9時半には終えられるように。最近また10時くらいまでかかる日も増えてきてるので、こっちもハッパかけていきたいと思ってます。
<対策3>
昼食を立ち食いに変更しました。元々食事へのこだわりが薄くて、毎年冬になるとずっと同じものを食べるという習慣があります。なのでもういっそ昼食は立ち食いで5分ほどで済ませるようにしました。散歩は欠かせないのであちこち出かけています。だいたい図書館に通うか、近所のスーパーで買い物を済ませるようにしています。そろそろ別の景色も見たいです。
<対策4>
目覚まし時計をかけるようになりました。今までは眠る時間が早すぎて4時〜6時には勝手に目が覚めていたのですが、それよりも夜更かしして朝は同じ時間に起きなくてはいけないようにしてみました。
と、これをフル活用するとなんとか1日あたり9.5時間ほど自分の活動時間を確保できる日ができるようになりました。
2〜3日に1回くらい子供達と一緒に寝落ちしてしまうので、毎日こんなベストに事が運ぶというわけではありませんが、まあここまでは動けるんだな、という実感が湧いてきたのは嬉しいです。
|
|
|
2024.01.08 ボロちゃん

ジブリ美術館で「毛虫のボロ」上映中とのことで行ってきました。
2018年制作のこの短編映画、2016年と2019年に出産してますからね、今まで産後にもたまにジブリ美術館は行ってましたが、あれこれタイミングが合うということはなくて見逃しつづけていました。やっと見れて感無量です。
SNSに感想書き込むのも未見の方に申し訳ないと思うので、こちらに書いておきます。
いやぁ、可愛かった。一言で言えばこれに尽きるのですが、その可愛さは何によってもたらされているのかといえば、ボロの小ささがとてもとても、とても丁寧に描かれている点に集結していくんだろうなと思います。
ボロは生まれたての毛虫だから1mmくらいだそうで、そのボロにはどんなふうに世界は映るのか、感じるのか、が視覚で表現されています。
我々人間には見えないものがボロには見えるんですね。まさに顕微鏡の中の世界。生物の資料集を覗いた時のあの緑の透明のキラキラした世界。私たち人間にとっては、日常の一場面にすぎないものも生まれたてのボロにはとても巨大で刺激的なものに思えるんだな、というのが全てのシーンから伝わってきます。
それから、世界の理である弱肉強食もしっかり描かれています。
食と排泄についてもね!
パンフレットを買って読んでみたら、宮崎監督はボロの視点から世界を見るとどうなるのか?それがおもしろいものになるのか?を結構不安に思いながらの制作だったようで、意外でした。
宮崎監督といえば、確かに悩む姿をテレビなどで拝見することはありましたが、今のこの世のこれがいけない!だから映画で新しい提案を!という確信とともに、悩んでいるような印象が強かったのですが、ボロのについてはただ監督がこうしてみたらどうだろう?という実験精神がスタートとなっていたようで、とても不安だったようです。
宮崎さんは先日83歳になられたわけですが、この時だって結構なお年。それでもまるで新人のように新鮮な気持ちで新しい作品を作り続けているのがすごいな、と思いました。
私の身の回り限定ですが「君たちはどう生きるか」は評価が二分しているように感じてます。私はそのどっちも感想として持っています。あそこまでご自分の世界観を素直に出してしまったという意味ではとても素晴らしいとも思ったし、アートアニメーションへの慕情もエンタメへの執念も捨てきれずに作られた、ひとりよがり気味な作品とも思っています。
でもねー、もうねー、作品どうこうということよりも、やっぱりこの人の生き方やものづくりの姿勢は本当にすごいなというところに来ましたよね。
先日のプロフェッショナルを見て、そう確信しました。過剰演出のフィルターなんて抜いて見ても、やっぱりすごい人だって十分伝わってくる内容でしたね。それから、いつのまにやら随分とイケメンになられてますよね。その人がどう生きてきたかの月日ってやっぱり顔の出るものなのだな、と実感しました。
私は今自分はあまり美人じゃないと思うんです。何を当たり前のこと言ってるんだという感じですが、前後の流れから意味を汲んでやっていただければ幸いです。若いって言われることは多いですが、つまり幼いんですよね。美人なおばあちゃんになりたいな、そういう生き方をしたいな、というのが最近のとても大きな目標です。
すっかりボロの感想から離れてしまいましたが、好きな映画がまたひとつ増えました。見に行けてよかったです。
|
|
|
2024.01.01 あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。
2024年もよろしくお願いいたします。
さて、私は過去を見る人間、ということで早速ですが2023年を振り返っていこうと思います。
周囲から次々と仕事納めの報告が入ってくる中、実は私はここ2ヶ月受注のお仕事をしていなかったもので、全く納めた気がしないままの年明けとなりました。
というのも、2023年はついに自分がやりたかったことと本気で向き合う年に変えようと決心したからなんです。
そうはいってもお金は稼がなきゃいけないし…しかしまだまだ子育て中の身、毎日本当に時間がないし…。
計算してみたら、安定して集中できる時間というのは1日あたり6時間だけでした。仮に独身時代のことも思い出しながら計算したら11時間ありました。毎日5時間違うって…さらに土日が完全停止になります。そんな状況下でずっと独身時代から年収変えずに来たってえらいね!と思ったりもしますが、つまりはやらなきゃいけないことばかり、やりたいこと募るだけの状況がもう何年も続いていたわけです。
このままじゃ嫌。はたしていい加減どうしたらやりたい方向へと舵を切れるかを考えました。
それで考えた挙句一旦
・自分の名前が出ないもの
・スケジュールをひきにくいもの
・予算が不十分と判断したもの
を基準に、受注する仕事をしばしお休みすることにしました。
そしたら仕事がなくなっちゃいました。上記のようなお仕事をずっとしてきてたんですね。
上記のようなお仕事もどれもとても立派な案件です。ただ持ち時間が圧倒的に少ない中で、ここに全てを捧げることは一度お休みして、自分からやりたいと思う仕事を増やそうと思いました。
というわけで、この2ヶ月無収入なくせに、自分のやりたい仕事へ向かう準備をずっとしているので相変わらず時間はありません。こどもからはかーちゃんがますます一緒に遊んでくれなくなった、と苦情が入っています。ごめんね。
さて、2023年ラスト2ヶ月の変化が大きすぎてそこばかりフォーカスしてしまうのですが、他にも本当にいろいろ変化があった1年でした。
1.自室ができた
長男の小学校入学に合わせてこども部屋を作りました。それに合わせて夫婦もそれぞれの部屋を持つことにしました。
各部屋ができた当初、私は子供部屋で一緒に寝ていたのですが、次男の夜泣きがいつまでも続くことなどを理由に、夏頃から夜中に一度起きたら自室へ移動し眠るように。その後だんだんとシフトして、今は自室で最初から眠るようになりました。今は夫と子供たちが一緒に寝ています。
以前は8時間以上眠っても夫のいびきはうるさいし、夜中蹴られてたり、夜泣きで起きたりと全然寝た気がしなかったのですが、今は6時間半くらいで同じくらいは回復するようになりました。元々よく眠る人なので、ほんとはもっと眠りたいですが。
2.大きな出会いがあった
渋谷にできた新しい施設CCBTというところで、この夏ワークショップをしました。企画展示に付随してだったのですが、その企画がこちら。
はい、わかる人はわかるでしょう、あの伝説のメディアアーティスト岩井俊雄さんの展示でした。ちょっと前の日記に書いた「とある人」とは岩井さんです。
でここでは少し話をずらして私と有名人のお話に。
なぜか昔から身の回りに「すごい人」「有名な人」が結構います。実家のお隣は中年以上の方なら誰でも知ってるであろう芸人さんが越してきて住んでます。
でもそういった「すごい人」に私はあまり臆した覚えがないです。なんでかな?と思い返したら、おそらく大学入学直後に出会ったカヌー日本代表選手達がとても気さくだったからじゃないかな?というところに辿りつきました。
大学入ってすぐ、なんとなく始めたカヌーの世界、競技人口が少ないので、ナショナルチーム(日本代表)の人がそのへんにいるんです。そしてちょうど同じくらいの年齢ということもありごくごく普通に友達に。彼らがもし、つっけんどんな態度をとるような人たちだったら私は今みたいにいろんな人と接することはできてなかったんじゃないかと思いました。ありがとう、Tさん、Sさん。
といいますか、何かしらすごいことを成し遂げてる人って、皆さん気さくで親切ですよね。
私もケチケチしてないで、そういうおおらかで朗らかな人になりたいです。
3.いくつかの悟り
42年近く生きてきて、生活や仕事の仕方を変えて見えてきたことがあります。
「ぎらぎらすることとやる気を示すことは違う」
いやぁ、今まで私ずっとギラギラでした。だからやりたいと思う仕事ほど続かなかったのかな?と思います。一方で下請けに頼れるだけ頼りたいといったお仕事はどんどん来るわけです。そうやって頼りにしていただけることに喜びも感じていましたが、とにもかくにも今は時間がない。そんな中でそういった類のお仕事だけで100%時間を埋められていくことは、やっぱりちょっと違うんじゃないかな、と思うようになったわけです。
「ご実家に頼れていいですねは禁句にしましょう」
これはね、いろいろあって思うようになりました。言われたこともあるし、言ったこともあります。でも近ければ近いほどトラブルもあるのが人間関係の常です。ましてや母親と娘という関係になったら…
なので個人的な決め事ではありますが、今後はこういった言葉は言わないし、自分も言われても無視していいことに決めました。
「アレルギー薬服用すると落ち込む」
これは、悟りなのか?といった感じですが、突然気づきました。去年の花粉シーズン以降、ずっと半量のアレグラを飲み続けていたんですね。飲まない日が3日ほど続くと前触れもなく鼻水だらけで何もできない日が来てしまうので。それがインフルで強いアレルギー薬出されたあと、1週間ほどやめてたんです。そのとき、とても頭がクリアでした。1週間後にまた鼻水がダーっと出てしまう日がきたのでアレグラ飲んでみたら、これがずーんと落ち込むのです。
あれ?ひょっとしてアレルギー薬って脳を鎮静化させる作用もある?と気づきました。
さてはて、今後どうするか。現在検討中です。
と、いうわけで2023年はいろいろ変化のあった年といいますか、自分を見つめ直した1年でした。
出会えた上昇海流(あえて気流ではない)にもっと上手に乗れればよかったのですが、乗ってる途中でおっとっと、と転げ落ちかけ、ジタバタとひとり泳ぎ始めたところです。
2024年は他人に作ってもらった海流ではなくて、自分で巻き起こした気流にのれるように頑張りたいと思います。努力の才能だけは、どうやら少しだけ多めにもらって、生まれてきたようなので!
|
|
≪HOME≫
|